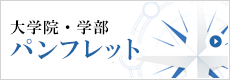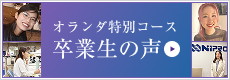大学院の紹介
学生からのメッセージ
長崎大学大学院多文化社会学研究科博士前期課程の在学生から、受験生へのメッセージを紹介します。
Invaluable Experiences in Nagasaki

Linguistic Diversity Course Group Second year [*FY2024]
SVIETLOVA MYROSLAVA
I am truly grateful for the opportunity to study at Nagasaki University. It is not just a place of learning but an environment that inspires new discoveries, broadens my horizons, and helps me grow as a researcher.
Studying here has given me invaluable experiences—from engaging with professors and students from diverse backgrounds to exploring my academic interests in greater depth. I especially appreciate the support and access to resources that have been instrumental in my research pursuits.
I am thankful to the university for this unique opportunity, and I hope to apply the knowledge and experience I have gained to contribute to my field of study in the future.
Nagasaki University offers a great support for its students

Linguistic Diversity Course Group First year [*FY2023]
LUHOVYK OLENA
Nagasaki University provides its students with a comfortable studying environment and facilitates studies in every possible way. Research laboratories and the University Library, where students can access lots of materials, are highly helpful. In addition, it has numerous well-qualified professors with whom studying becomes fascinating and in my experience every professor is eager to help their students with any course-related or research-related questions. It is always reassuring to know that if I ever feel stuck with my research, I can always count on experience, knowledge and kind hearts of SGHSS professors
The University does an excellent job of meeting students’ individual needs in every possible way through counselling, access to primary health care in the on-campus Medical Center and consultations in the Student Support Division.
Another remarkable point is the University administration’s efforts to integrate international students by organizing Japanese Language and culture classes, workshops, and other investing and helpful events.
自分の研究だけにとどまらず、より多角的な側面から社会を理解し考えよう

グローバル・スタディーズ科目群 1年(※2022年度)
周 晴
私は北京外国語大学の日本語学院を卒業し、本研究科に進学しました。今は日本社会における宗教の社会貢献活動について研究を進めています。
大学時代から、社会学に関心を持っていました。卒業論文の研究をさらに一歩進めようと思い、研究計画書を書きました。その際、異なる学術分野を横断的に繋ぎ、現代社会を俯瞰的な観点から捉えるこの多文化社会学研究科に魅了され、進学する決意をしました。
本研究科では、自分の専攻に限らず、国際関係、移民研究、統計分析等、学際的な視野を広げるための科目を履修することができます。履修人数に関わらず開講するため、時には一対一の対話型授業を取ることができます。これらの科目は、私の研究に様々な視点を与えたのみならず、より多角的に社会を理解し、考えることを可能にしてくれました。
また、研究科の自由に話し合う雰囲気に魅了されています。研究科の先生と学生が集まって学際的に議論する「多文化社会学セミナーⅠ、Ⅱ」のほか、学生のみの研究室においても、院生同士で研究について自由に意見交換をすることもできます。
考古学的な視点のみならず、多角的に社会問題を研究したい

環海日本長崎学・アジア研究科目群 1年(※2021年度)
賈 文夢
私は、長崎大学多文化社会学部で2年間、研究生として過ごし、本研究科に進学しました。今は野上建紀教授の研究室で考古資料を元に、江戸時代に天然痘を患い亡くなった人々の墓、いわゆる「疱瘡墓」の研究を進めています。
地球で生活する我々人間は常にいろんなウイルスとともにありました。江戸時代の天然痘は強い感染症として恐れられ、大村藩などでは感染した人は厳しく隔離され、死後も人里離れた場所に埋葬されました。その「疱瘡墓」から当時の差別と隔離を考えたいと思います。
現代の新型コロナ感染症をみてもわかるように、感染症はひとつの国や地域の問題だけではなく、世界中が直面する問題です。感染症との闘いの遺産とも言える「疱瘡墓」からみる感染症対策は、現在の新型コロナ感染拡大への対応など現代的な課題とも重なります。
私の専門は考古学ですが、多文化社会学研究科では歴史学、文化人類学、社会学など様々な専門科目を学べます。この環境を生かしながら考古学的研究から学際的研究に展開させたいと思います。
日本の先進的知識・技術を習得し、両国の次世代に伝え続けていきたい。

環海日本長崎学・アジア研究科目群 1年(※2020年度)
鄭 祝昂
小さい頃から、日本のドラマが大好きな母の影響を受けて、日本語をはじめ様々な日本文化に心を惹かれ、今では憧れの国と言えるほど日本に対して好印象を持っています。
中国の大学を卒業後に日本に留学し、1年間の研究生を経て、2020年4月から多文化社会学研究科博士前期課程に在籍しています。研究科では、環海日本長崎学・アジア研究科目群を中心に、主に東アジアの国際関係を学んでいます。文化・政治の両面での共生を意識し、バランスをよく取り、相互に助け合うことが大事だと考えています。
現在、日中の友好都市交流における文化の役割をテーマに研究を進めています。遣唐使の時代から戦前まで、多くの日本人・中国人留学生が、誤解やトラブルを解決できるよう相互に努力してきました。戦前から中国と深い繋がりのある長崎の地だからこそ、自分の答えが見つかると思っています。
卒業後は、先輩たちのように、日本の先進的知識・技術を習得し、両国の次世代に伝え続けていきたいと考えています。
「権力/知」の覇権を脱構築し、差別のない世界を構築しよう

政策科学科目群 2年(※2020年度)
劉 京
私は、中国の天津師範大学から日本に留学して、その後本研究科に進学しました。今、中国におけるクィア理論の適応性について研究を進めています。
世の中における権力の配置は、ジェンダーやセクシュアリティについての思考の枠組みになっている男女の二元論を産出し、主体や他者や「男/女」の二元的関係などの内的安定さをパフォーマティヴに構築しています。クィア理論はそれらのカテゴリーを脱自然化、脱構築し、二分法の枠組みを超えた撹乱的な再意味付けや、意味の増殖の契機を提示しています。
「人間は生まれながらに平等である」。多文化共生の世界とは、差異をもつ人々が、文化的な違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、共に生きていく世界です。私から見れば、「共生」の「生」は「生存」ではなく、楽しく「生活」することです。ゆえに、人種や国籍だけではなく、性別、性的指向、階層言語などのカテゴリーにおけるマイノリティへの差別をなくし、誰もが尊敬され、過ごしやすい社会を実現していくのが多文化社会学の広義な射程だと思います。
日中のかけ橋となり両国間の理解・交流に力を尽くしたい

政策科学科目群 2年(※2019年度)
馬 継銘
私は、中国から日本へ留学し、日本語学校での勉強を経て、多文化社会学研究科へ入学しました。学部ではジャーナリズムを専攻し、編集者・記者の仕事を目指しています。この研究科では日本、中国などのアジア諸国だけではなく、世界中の様々な国が研究対象であり、私たちの社会では「当たり前」のことを再考しています。これは編集者・記者にとって必要不可欠なことだと考えています。
この研究科では、自分の専門分野以外も学べます。昨年は国立歴史民俗博物館で開講された「総合資料学」を受講しました。博物館の先生が分かりやすい事例で教えてくださいますので、歴史が専門でなくても気軽に受講できます。「総合資料学」はある分野·学問について研究するのではなく、多様な学問を統合した上の学問なので、どんな分野を研究する人にとっても役に立つと思います。
現在は、中国のネットにおける市民社会について研究しています。日本、そして長崎にいるからこそ発見できる問題が必ずあると思います。卒業後は日中のかけ橋となり、両国間の理解・交流のために力を尽くすメディアの一員として働きたいと考えています。
平和活動の経験と研究科での学びを通して核軍縮・不拡散教育を考える

核軍縮・不拡散科目群 1年(※2019年度)
光岡 華子
私は長崎大学教育学部を卒業し、この多文化社会学研究科に進学しました。学部時代は、それまで関心のあった“平和”について長崎の視点から学び、Peace Caravan 隊という団体で、現在の核問題にもフォーカスした平和出前講座を各地で行ってきました。より多くの人に核の問題は今の問題であり、 私たち自身の問題であると捉え、考えてもらえるように励み、教育者、発信者となることの意義を体感しました。
しかし、活動を重ねていく中で「核兵器はなぜダメなのか」「どうすれば廃絶できるのか」という問いに対する 自分の考えの浅はかさを痛感しました。大学院への進学を決意したのは、自分が当然のように受け止めていることを問い直し、深める機会が必要だと思ったからです。
これまで活動的に過こしてきた私にとって、大学院での答えのない問いに向き合い考える時間は、新鮮でとても楽しいです。学部時代の経験とこれからの学びを活かして、「非政治化するナガサキの平和教育」についての研究を深めていきたいと思います。
言語学的な視点のみならず多様な考えを身に付けたい

言語多様性科目群 2年(※2019年度)
安部 健太朗
私は、多文化社会学部を卒業して、大学院へ進学しました。学部の授業では、人文系学問の基礎的な知識を学びました。それらは、現代の学問における重要な基礎知識であるため、大学院の講義、「学問のエレメンツ」でもたびたび耳にします。学部と大学院の重要な違いは、その内容の深度にあると思います。「学問のエレメンツ」では、諸学問のベースとなる哲学であるメタ理論(存在論、認識論、方法論)を中心に勉強します。すべての学問の根底部分には哲学が存在します。それらを学習することによって、学問を根底から再構成し、多文化社会学という新しい学問を作り上げていこうというのが、大学院の狙いです。
このようなカリキュラムで勉強できるのは、おそらく多文化社会学研究科だけです。人文科学を領域横断的に学べるので、自分の専門分野以外の考え方も学ぶことができ、学びが充実しています。私は、言語学の第二言語習得論を研究しています。言語学的な視点のみならず、幅広い学問に触れることによって多様な考え方を身に付けたいと考えています。