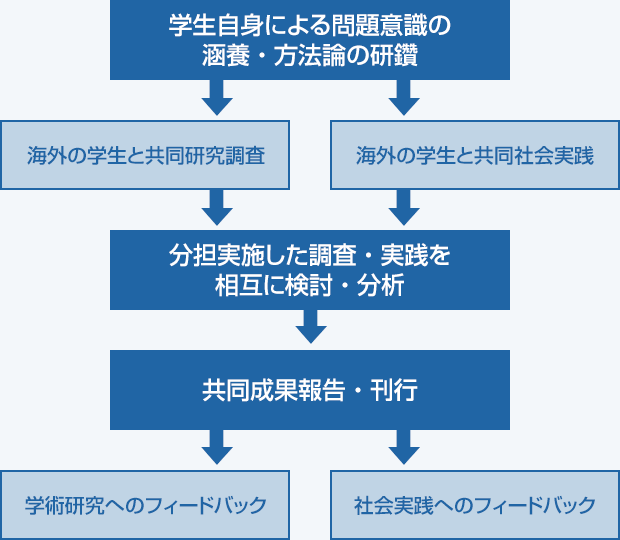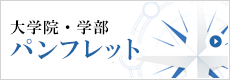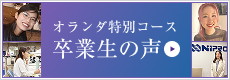大学院の紹介
特色ある教育
多文化社会学セミナー
〈学問のプラクティス〉の科目群は、機動的に学びの枠組みを編成する開放的プログラムとして構成され、その実践的総括は、必修科目「多文化社会学セミナー」を通じて実施します。
「多文化社会学セミナー」では〈学問のエレメンツ〉で学んだ専門知、技法、領域横断的枠組みの土台の上で、多文化社会的状況における諸問題の実践的解決法の習得に向けて、ケーススタディ、ディスカッション、レクチャー、ネットワーキングパーティを領域横断的に実施します。
【ケースメソッド(ディスカッション・スタイル)の例】
「宗教に関わる多文化社会的状況とその諸問題の解決に向けて」
宗教対立/紛争、原理主義、テロリズムについて、領域横断的に学生と教員がディスカッション
◆移民:人の移動による異なる価値観の接触
◆貧困:世界規模で進展する経済格差
◆つながりの喪失とマイノリティの孤立
◆アイデンティティのゆらぎ
◆拒絶反応としての排外主義
↓
過激な宗教的表現へ
『現代世界特有のリスクを回避しながら、社会がいかに存続可能か』という普遍的かつ喫緊の課題を明確化する
・主に中東やヨーロッパで顕在化している宗教的問題は「どこででも起こりうる」
・自然災害のリスクにも適用可能 (東日本大震災の例)
〈学問のエレメンツ〉の成果に基づきつつ、〈学問のプラクティス〉を統合・展開していく―研究の総括に向けて
・各専門知を横断する存在論・認識論への再埋め込みと、分野横断的な包括的枠組みの新たな構築を通じて、ケースメソッドに参加した教員や学生が、グループワークなどを通して、それぞれの解決方法を提言
・特定の指標(宗教、民族、経済、政治、教育、…)による定量的および定性的な分析の統合
・対象の「部分」と「全体」を包括的に捉える視座の明確化(現地の歴史的要因とグローバルな要因の交錯する場として)
・政策研究(policy study)や政策分析(policy analysis)を通じて、政策課題やその費用対効果、政策の適切な方法を議論
・領域を横断して指導を受けることができる総合研究指導体制、PDCAに基づく明確な里程標の設定
・全学生を対象にして、修士論文執筆に向けた研究の質保証を徹底
海外経験選択科目
文化的言語的他者とのコンタクトやインタラクションを通して、卓越した語学力や情報収集分析力、多様性や環境への深い認識と文化や他者への深い共感を学びます。
具体的な内容 <海外フィールドワークによるアクティブラーニング>
【従来】
教員側が中心となって海外の社会や文化を一方的な研究対象とみなす取組み

【今回】
学生が自ら問題提起し、海外の学生との「双方向性」を重視しつつ、プロジェクト的運営を実施