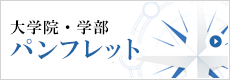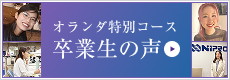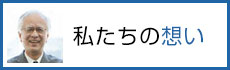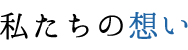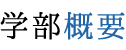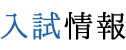学部紹介
社会動態コース
社会学、文化人類学、歴史学を中心に学び、アジアからアフリカ、ヨーロッパにかけての社会の変化を、フィールドワークを通して実践的に理解します。国際的なコミュニケーション力と実践力を身につけた人材を育成します。

【異文化と家族】
先入観から自分自身を引き離す能力と
文化的な他者と生きる能力を磨きましょう。
賽漢卓娜 教授
多文化社会学部で先入観から自分自身を引き離す能力と、文化的な他者と生きる能力を磨き、高めることを学生に求めています。自らのライフデザインをしっかり考え、真の多文化共生社会を構築していくための人材として力を発揮してほしいと思います。
コースの特色
長い歴史において、ヒトやモノや情報は、常に移動を繰り返してきました。世界のどこかで発生した小さな変化が、人々の行動や情報伝達を通じて他の場所で大きな、思いもよらぬ変化をもたらしたりします。こうした全体的な変化のあり方を「社会動態」といいます。
このコースでは、「社会動態」を学ぶために、フィールドワークによる問題発見、調査、成果公表のスキルを身につけることを重視し、国際的なコミュニケーション力と実践力を備えた人材育成を目指しています。
講義科目

■国際社会学
■異文化理解教育
■境界文化論
■異文化と家族
■現代アフリカ社会論
■現代アジア社会論
■陶磁考古学
■グローバル文化交流史
■ヨーロッパ近現代史
■異文化交流論
■文化資源論
■地域生態論
■宗教文化論
■地域史料論
※科目名称は変更する場合があります。
※青字は複数コースにまたがる専門講義科目
在学生の声

横断的な知識を学び
新たな発見と出会う
伊藤 優花(4年)※2021年度現在
学校法人筑紫女学園出身
社会動態コースでの学びは、自分の生活や身近なものに対する気づきを与えてくれます。こうした新たな視点を持つことで、 3年次の中長期留学がより充実した内容となりました。卒業論文のテーマは、ドイツにおける人権とアジア人差別です。これまで学んできたインタビューやアンケート調査の手法を取り入れながら進めていきます。
在学生の声(2020年度)

生活と結びついた文化を
フィールドワークで調査
田上 奈々加(4年)
熊本市立必由館高等学校出身
留学先:中国/上海師範大学
私の卒業研究のテーマも身近なもので、日本と中国のアイドルファンのコミュニティについて比較や分析を行っています。2年次に中国の上海師範大学に留学し、実際に現地のライブに参加したり、中国人のファンへのインタビュー調査を実施しました。日本との違いを体感しながら学ぶことで、新しい視点で研究を進めることができています。将来は、日本と海外を助け合える関係として繋げられるような仕事で活躍したいです。
在学生の声(2019年度)

観光を学問的に研究し、
地域のまちづくりに活かす
山根 涼加(4年)
姫路市立姫路高等学校出身
留学先:オーストラリア/ウェスタンシドニー大学
以前からまちおこしとしての観光に関心があり、文化人類学や社会学、民俗学などを深く学べるコースで観光をアカデミックに研究したいと思っていたからです。また、1年次に受けた社会動態コースの講義の面白さや、自分の関心と類似した先輩の研究テーマに興味をひかれたこともコース選択の後押しとなりました。
印象に残っている講義は、「文化は社会の鏡なのか」(現在の「文化人類学基礎(民族誌)」)です。伝統的な名産品の成り立ちについての解説があり、古くから親しまれているように思える名産品も歴史が浅かったり、後から構築されたものもあると初めて知り衝撃を受けました。また、高校と違って大学ではアウトプットの機会が多く、レポートやディスカッションを通して成長することもできました。
卒業後は英語力を活かしながら、地域の魅力を発信する仕事を目指しています。
在学生の声(2018年度)
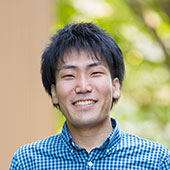
人々の暮らしと環境が密接に結びついている
アフリカ社会について同時代性を意識しながら考える
宮城 敬(4年)
沖縄県・昭和薬科大学附属高等学校出身
留学先:アメリカ/ベネディクティン大学
本コースの地域生態論という授業では、アフリカの狩猟採集民や牧畜民が変わりゆく環境にいかに柔軟に適応し、生活しているかについて事例を通じて学びます。私たちが普段イメージするアフリカとは違う側面からアフリカについて学ぶことができ、とても魅力的な授業です。
卒業後は、現在の研究テーマをより発展させるために、大学院に進学したいと考えています。そして、どのような形であれ、今後もアフリカに関わり続けたいと思っています。
在学生の声(2017年度)

【アジア海域交流史】
※平成30年度より科目名「陶磁考古学」に変更予定
考古学的視点から近世海上ネットワークの様相を導き出し、グローバル化について考える。
岡田 淳希(4年)
長崎県・青雲高等学校出身
留学先:タイ/カセサート大学
この講義では中世から近世のアジアにおける海上交流ネットワークの特質を考古学の視点から遺物を元に導き出し、現代のように発達した技術がないのにも関わらず何故、そしてどのように異なる文化同士が交流したのかを考察します。
必ずしも多くを語らない遺物から歴史的事実を推測するのは面白くもあり、同時に難しくもあります。遺物から見えてくる歴史を通して“グローバル化とは何か”に対する自分なりの考えを養うことができます。