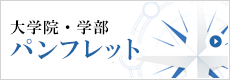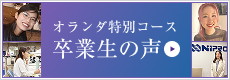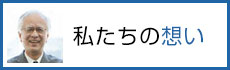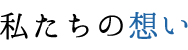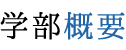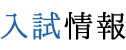学部紹介
教員紹介
阪野 祐介

宗教と社会の関係を人文地理学の視点から読み解く
阪野 祐介(さかの・ゆうすけ)
北海道旭川市生まれ。博士(文学)。専門は、人文地理学(宗教地理学・歴史地理学)。新潟大学人文学部卒業。神戸大学大学院文化学研究科博士課程修了。関西諸大学での研究員、非常勤講師、および韓国・釜山にある韓国海洋大学校での勤務を経て、2025年4月より長崎大学多文化社会学部(宗教学分野)に着任。
⇒研究歴等の詳細へ
Q.ご自身の研究を紹介してください。
~“宗教地理学!?”~
聞きなれない言葉かもしれませんが、宗教地理学を専門領域としながら、宗教と社会の諸関係のありようの地理的(地域的・空間的・景観的)な特徴を探る研究をおこなっています。これまで、山そのものを神とする、あるいは神のいる場所として山を信仰対象とする山岳信仰の空間構造や地域的差異に関する研究、農村におけるカトリックへの集団改宗、キリシタン殉教地の聖地化、儀礼と国家などのテーマを扱ってきました。現在は、長崎県をはじめとしたカトリック/キリシタン集落の空間構造とその変容、九州の山岳信仰に関心をもって調査・研究をすすめています。これらの研究を通して、日本社会の宗教的特徴を明らかにすることを目指しています。
~“近代東アジア海港都市における地域表象および異文化接触に関する研究”~
もう一つ取り組んでいるテーマが、近代東アジアの海港都市、とくに植民地期朝鮮に関する研究です。このテーマでは、ポストコロニアルの視点から植民地における権力と空間の関係や、多様な主体が交差する海港都市における人びとのくらしや異文化接触の様相を探り、近代都市における近代的経験を明らかにすることを目指しています。具体的には、都市形成過程と空間構造、植民地ツーリズムと表象、植民地神社と地域社会について調査・分析を行っています。この研究では、都市図や観光案内図といった視覚的資料を用いて分析を行う点が特徴にもなっています。
聞きなれない言葉かもしれませんが、宗教地理学を専門領域としながら、宗教と社会の諸関係のありようの地理的(地域的・空間的・景観的)な特徴を探る研究をおこなっています。これまで、山そのものを神とする、あるいは神のいる場所として山を信仰対象とする山岳信仰の空間構造や地域的差異に関する研究、農村におけるカトリックへの集団改宗、キリシタン殉教地の聖地化、儀礼と国家などのテーマを扱ってきました。現在は、長崎県をはじめとしたカトリック/キリシタン集落の空間構造とその変容、九州の山岳信仰に関心をもって調査・研究をすすめています。これらの研究を通して、日本社会の宗教的特徴を明らかにすることを目指しています。
~“近代東アジア海港都市における地域表象および異文化接触に関する研究”~
もう一つ取り組んでいるテーマが、近代東アジアの海港都市、とくに植民地期朝鮮に関する研究です。このテーマでは、ポストコロニアルの視点から植民地における権力と空間の関係や、多様な主体が交差する海港都市における人びとのくらしや異文化接触の様相を探り、近代都市における近代的経験を明らかにすることを目指しています。具体的には、都市形成過程と空間構造、植民地ツーリズムと表象、植民地神社と地域社会について調査・分析を行っています。この研究では、都市図や観光案内図といった視覚的資料を用いて分析を行う点が特徴にもなっています。
【PHOTO】江戸時代末に潜伏キリシタン集落であった神ノ島の聖堂と岬の聖母像(2014年1月阪野撮影)
Q.どのような授業になりますか。
専門科目「宗教文化論」
近代以降、「宗教」と社会の関係はより複雑で多様な様相を見せるようになりました。宗教の衰退が世俗化として指摘される一方で、“宗教の復権”“宗教ナショナリズム”などに示されるように宗教と国家の結びつきが強まったり、政教分離のあり方が問われたり、あるいはスピリチュアリティやパワースポットブームなど既存の宗教とは異なる「宗教的なるもの」が生まれたりもしています。また、日本国内をみても近年のインバウンドや移民の増加により多様な文化的・宗教的背景を持つ人々との接触する場面がますます増えています。そうしたことからも宗教について学ぶことは非常に重要であるといえます。それゆえ、この授業では、宗教と社会の諸関係、具体的には世界観と表象、宗教と移民・都市空間、宗教と観光、宗教と政治について理解を深めることに重点をおきます。
また宗教学関連の授業のほか、日韓文化関係論、韓国でのフィールドワークを担当し、日韓学生交流の場なども今後企画していければと思っています。
また宗教学関連の授業のほか、日韓文化関係論、韓国でのフィールドワークを担当し、日韓学生交流の場なども今後企画していければと思っています。
Q.メッセージをお願いします。
IT技術の発展とAIの進展により、われわれは多くのさまざまな情報に容易にアクセスできるようになりました。だからこそ書物をじっくり読み、思考を深めることを、またフィールドに出て、⾒て、感じて、⾏動することを、そして⼀つ⼀つの出会いを⼤切にしていきましょう。