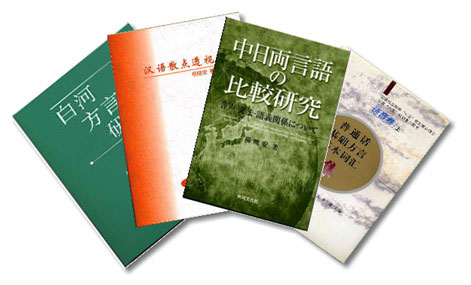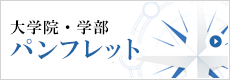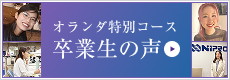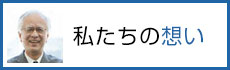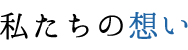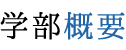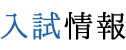学部紹介
教員紹介
楊 暁安

日中の言語を比較し、言葉の構造を探究する
楊 暁安(よう・ぎょうあん)
中国出身。博士(文学)。中国西北大学文学部副教授、福井大学教育学部外国人教師、北海道文教大学外国語学部教授を経て長崎大学言語教育研究センター教授。研究分野は応用言語学・実験音声学・中国語教育。
⇒研究歴等の詳細へ
Q.ご自身の研究を紹介してください。
日中両言語の比較研究―音声と語義と文法の関係について
私の研究分野は応用言語学で、この数年間、「音声と文法・語義の関係」の研究に取り組んでいます。
具体的には、実験音声学の手法を用いて、音声分析ソフトによる音声分析や合成などを通して、中日両言語の音声構造の違いや連続発話における音変化などについて比較しています。特に両言語の音声の高さと強さの変化、音声の継続時間の比率関係の変化など、中国語と日本語が、異なる文法構造と語義を示す際にどのような音声の特徴を示すかを比べながら、語音手段と文法・語義の関係について研究しています。
具体的には、実験音声学の手法を用いて、音声分析ソフトによる音声分析や合成などを通して、中日両言語の音声構造の違いや連続発話における音変化などについて比較しています。特に両言語の音声の高さと強さの変化、音声の継続時間の比率関係の変化など、中国語と日本語が、異なる文法構造と語義を示す際にどのような音声の特徴を示すかを比べながら、語音手段と文法・語義の関係について研究しています。
Q.どのような授業になりますか。
専門科目「対照言語学」
いかなる言語もそれぞれ独特の構造システムと、固有の文法構造、そして意味表現の特徴を持っています。こうした構造と特徴は、結局は音声形式を通して実現されます。つまり文法構造や意味表現と音声形式とは密接に関連していて分かつことは出来ないのです。
この授業では日中両言語を比較しながら、実験音声学の方法を用いて両言語の音声構成、変化がどのように語義や文法の変化を引き起こすかを観察し、分析する能力を養えるようにしたいと思います。
この授業では日中両言語を比較しながら、実験音声学の方法を用いて両言語の音声構成、変化がどのように語義や文法の変化を引き起こすかを観察し、分析する能力を養えるようにしたいと思います。
【PHOTO】著書
Q.メッセージをお願いします。
「学而不思則罔、思而不学則殆」――『論語・為政篇』
「勉強するだけで自ら考えなければ、物事の道理が身につかず、考えるだけで勉強しなければ、独断的になって危険である。」これは中国の偉大な思想家・教育者の孔子が2500年前に言った言葉です。自分の頭で考えることなしにただ知識を詰め込むばかりでは物事の本質は見えず、表面的なものしか身につきません。逆に、先人の知恵に学ばずに自分で考えてばかりいると、知識を得られず視野が狭くなってしまいます。
学生のみなさん、自分の頭で考え、語り合い、共に勉強していきましょう。
「勉強するだけで自ら考えなければ、物事の道理が身につかず、考えるだけで勉強しなければ、独断的になって危険である。」これは中国の偉大な思想家・教育者の孔子が2500年前に言った言葉です。自分の頭で考えることなしにただ知識を詰め込むばかりでは物事の本質は見えず、表面的なものしか身につきません。逆に、先人の知恵に学ばずに自分で考えてばかりいると、知識を得られず視野が狭くなってしまいます。
学生のみなさん、自分の頭で考え、語り合い、共に勉強していきましょう。