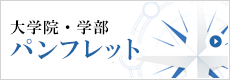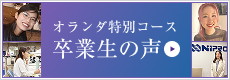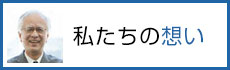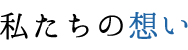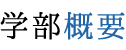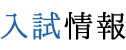大学院の紹介
教員紹介
才津 祐美子
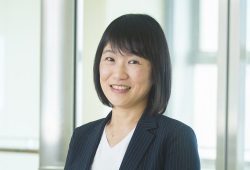
地域文化から日本、さらには人間を探究する
才津 祐美子(さいつ・ゆみこ)
長崎県生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。専門は民俗学、文化人類学。福岡工業大学社会環境学部、長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科を経て2014年4月より長崎大学多文化社会学部。主著書として、『世界遺産時代の民俗学』(風響社、2013年、共著)、『日本文化の人類学/異文化の民俗学』(法藏館、2008年、共著)『ふるさと資源化と民俗学』(吉川弘文館、2007年、共著)などがある。
⇒研究歴等の詳細へ
| 職位 | 教授 |
|---|---|
| 学位 | 博士(文学) |
| 専攻 | 日本民俗学、文化人類学 |
| 研究分野 | 文化遺産、文化政策、観光 |
| 担当授業科目 (博士前期課程) |
文化遺産論特講、文化遺産論特定演習、多文化社会学セミナー、研究指導 |
| 担当授業科目 (博士後期課程) |
研究演習Ⅰ、研究演習Ⅱ、研究指導 |
研究テーマ
近現代日本における地域文化の表象・継承・活用のあり方。とりわけ地域文化の文化遺産化や(観光)資源化について関心を持っている。
研究の内容や方法
(1)近現代日本の文化遺産保護制度(とくに、民家、伝統的建造物群、民俗文化財に関するもの)の変遷に関する研究(文献資料調査)。
(2)近現代日本における地域文化の表象に関する研究(文献資料調査)。
(3)地域文化の文化遺産化の影響や観光資源としての活用に関する研究(現地でのフィールドワーク)。主な調査地は岐阜県大野郡白川村、長崎県長崎市外海地区、長崎県五島市。
(4)(1)、(3)にもとづく、文化遺産保護制度の理念の実践のずれに関する研究。
(5)年中行事や信仰などの継承に関する研究(現地でのフィールドワーク)。
(2)近現代日本における地域文化の表象に関する研究(文献資料調査)。
(3)地域文化の文化遺産化の影響や観光資源としての活用に関する研究(現地でのフィールドワーク)。主な調査地は岐阜県大野郡白川村、長崎県長崎市外海地区、長崎県五島市。
(4)(1)、(3)にもとづく、文化遺産保護制度の理念の実践のずれに関する研究。
(5)年中行事や信仰などの継承に関する研究(現地でのフィールドワーク)。
研究成果
【主たる著書】
・長崎大学多文化社会学部編、木村直樹責任編集2018年『大学的長崎ガイド-こだわりの歩き方』昭和堂(「第2部 キリスト教の受容と展開-世界遺産への道のりをたどる」pp.133-149、「コラム 枯松神社-潜伏キリシタンから続くかくれキリシタンの聖地」pp.150-152を執筆。)
・香川雅信、飯田義之編、小松和彦、常光徹監修2017年『47都道府県・妖怪伝承百科』丸善出版(「第2部 都道府県別 妖怪伝承とその特色 長崎県」pp.275-280を執筆。)
・飯田卓編2017年『文化遺産と生きる』臨川書店(「第3部 世界遺産のまもり方-民家の移築保存と現地保存をめぐって」pp.233-261を執筆。)
・葉柳和則編2017年『長崎-記憶の風景とその表彰』晃洋書房(「第10章『長崎の教会群』世界遺産推薦取り下げから見えてくるもの」pp.291-319を執筆。)
・鈴木正崇編2015年『アジアの文化遺産-過去・現在・未来-』慶應義塾大学出版会(「第11章『白川郷』で暮らす-世界遺産登録の光と影」pp.359-386を執筆。)
・大橋昭一ほか編2014年『観光学ガイドブック-新しい知的領野への旅立ち-』(「第Ⅴ部第12章 世界遺産」pp.270-273を執筆。)
・岩本通弥編2013年『世界遺産時代の民俗学-グローバル・スタンダードの受容をめぐる日韓比較-』風響社(「第9章 日本における文化的景観保護制度の展開と課題」pp.277-302を執筆。)
・ほろよいブックス編集部編2012年『ほろよいブックス酒読み-文学と歴史で読むお酒-』社会評論社(「第Ⅲ部 禁じられた酒造りと許された酒造りの間」pp.80-95を執筆。)
・王暁葵、何彬編2010年『现代日本民俗学的理论与方法』學苑出版社(「世界遗产“白川乡”的“记忆”」pp.299-325を執筆。)
・神田孝治編2009年『観光の空間-視点とアプローチ-』ナカニシヤ出版(「第18章 世界遺産『白川郷』にみる文化遺産化と観光資源化」pp.201-210を執筆。)
・小松和彦還暦記念論集刊行会編2008年『日本文化の人類学/異文化の民俗学』法藏館(「第Ⅳ部 白川村発見-『大家族制』論の系譜とその波紋-」pp.430-451を執筆。)
・岩本通弥編2007年『ふるさと資源化と民俗学』吉川弘文館(「第5章 世界遺産という『冠』の代価と住民の葛藤-『白川郷』の事例から-」pp.105-128を執筆。)
・高多理吉ほか編2006年『社会環境学への招待』ミネルヴァ書房(「第5章 文化遺産の保護から考える環境としての文化」pp.160-171を執筆。)
・内田忠賢編2003年『よさこいYOSAKOI学リーディングス』開成出版(「第3部 『よさこい』の比較研究 祭りの『旅』-『ねぶた』『よさこい』の遠征・模倣・伝播」pp.66-102を阿南透、矢島妙子、内田忠賢と共著。)
・岩本通弥編2003年『現代民俗誌の地平3-記憶』朝倉書店(「第9章 世界遺産『白川郷』の『記憶』」pp.204-227を執筆。)
・長崎大学多文化社会学部編、木村直樹責任編集2018年『大学的長崎ガイド-こだわりの歩き方』昭和堂(「第2部 キリスト教の受容と展開-世界遺産への道のりをたどる」pp.133-149、「コラム 枯松神社-潜伏キリシタンから続くかくれキリシタンの聖地」pp.150-152を執筆。)
・香川雅信、飯田義之編、小松和彦、常光徹監修2017年『47都道府県・妖怪伝承百科』丸善出版(「第2部 都道府県別 妖怪伝承とその特色 長崎県」pp.275-280を執筆。)
・飯田卓編2017年『文化遺産と生きる』臨川書店(「第3部 世界遺産のまもり方-民家の移築保存と現地保存をめぐって」pp.233-261を執筆。)
・葉柳和則編2017年『長崎-記憶の風景とその表彰』晃洋書房(「第10章『長崎の教会群』世界遺産推薦取り下げから見えてくるもの」pp.291-319を執筆。)
・鈴木正崇編2015年『アジアの文化遺産-過去・現在・未来-』慶應義塾大学出版会(「第11章『白川郷』で暮らす-世界遺産登録の光と影」pp.359-386を執筆。)
・大橋昭一ほか編2014年『観光学ガイドブック-新しい知的領野への旅立ち-』(「第Ⅴ部第12章 世界遺産」pp.270-273を執筆。)
・岩本通弥編2013年『世界遺産時代の民俗学-グローバル・スタンダードの受容をめぐる日韓比較-』風響社(「第9章 日本における文化的景観保護制度の展開と課題」pp.277-302を執筆。)
・ほろよいブックス編集部編2012年『ほろよいブックス酒読み-文学と歴史で読むお酒-』社会評論社(「第Ⅲ部 禁じられた酒造りと許された酒造りの間」pp.80-95を執筆。)
・王暁葵、何彬編2010年『现代日本民俗学的理论与方法』學苑出版社(「世界遗产“白川乡”的“记忆”」pp.299-325を執筆。)
・神田孝治編2009年『観光の空間-視点とアプローチ-』ナカニシヤ出版(「第18章 世界遺産『白川郷』にみる文化遺産化と観光資源化」pp.201-210を執筆。)
・小松和彦還暦記念論集刊行会編2008年『日本文化の人類学/異文化の民俗学』法藏館(「第Ⅳ部 白川村発見-『大家族制』論の系譜とその波紋-」pp.430-451を執筆。)
・岩本通弥編2007年『ふるさと資源化と民俗学』吉川弘文館(「第5章 世界遺産という『冠』の代価と住民の葛藤-『白川郷』の事例から-」pp.105-128を執筆。)
・高多理吉ほか編2006年『社会環境学への招待』ミネルヴァ書房(「第5章 文化遺産の保護から考える環境としての文化」pp.160-171を執筆。)
・内田忠賢編2003年『よさこいYOSAKOI学リーディングス』開成出版(「第3部 『よさこい』の比較研究 祭りの『旅』-『ねぶた』『よさこい』の遠征・模倣・伝播」pp.66-102を阿南透、矢島妙子、内田忠賢と共著。)
・岩本通弥編2003年『現代民俗誌の地平3-記憶』朝倉書店(「第9章 世界遺産『白川郷』の『記憶』」pp.204-227を執筆。)
【主たる論文】
上記、長崎大学研究者総覧データベース(外部リンク)を参照。
上記、長崎大学研究者総覧データベース(外部リンク)を参照。
【外部資金獲得、受賞等】
科学研究費補助金
・平成28年4月-平成31年3月 (基盤研究(C))16K03225 研究課題:かくれキリシタンの近代における変化と文化遺産化に関する民俗学的研究 研究代表者
・平成26年4月-平成30年3月 (基盤研究(C))26520107 研究課題:高齢化が進む離島集落の再編に資する横断的研究(研究代表者:安武敦子(長崎大学)) 研究分担者
・平成26年10月-平成28年3月(予定) (研究活動スタート支援)26884034 研究課題:生きている信仰・カクレキリシタンの文化遺産化と世界遺産の影響に関する民俗学的研究 研究代表者
・平成25年4月-平成28年3月(予定) (挑戦的萌芽研究)80128181 研究課題:戦争記憶の表象における社会的マイノリティの位置-長崎をフィールドとして(研究代表者:佐久間正(長崎大学)) 研究分担者
・平成24年4月-平成27年3月(予定) (挑戦的萌芽研究)24653120 研究課題:メモリー・スタディーズのモデル構築に向けた領域横断的研究―東アジアを事例として(研究代表者:葉柳和則(長崎大学)) 研究分担者
・平成23年4月-平成26年3月 (基盤研究(B)(一般))23310035 研究課題:世界自然遺産の再資源化に向けたアクションリサーチ(研究代表者:柴崎茂光(国立歴史民俗博物館)) 研究分担者
・平成22年4月-平成25年3月 (基盤研究(C)(一般))22520827 研究課題:茅葺き技術の継承と応用に関する民俗学的研究 研究代表者
・平成20年4月-平成23年3月 (基盤研究(B)(一般))20320133 研究課題:文化財保護制度における世界遺産条約の戦略的受容と運用に関する日韓比較研究(研究代表者:岩本通弥(東京大学)) 研究分担者
・平成19年4月-平成22年3月 (若手研究(B))19720236 研究課題:「合掌造り」を事例とした近代における民家の価値転換に関する民俗学的研究 研究代表者
・平成18年4月-平成20年3月 (基盤研究(B)(一般))18320141 研究課題:家族写真の歴史民俗学的研究(研究代表者:川村邦光(大阪大学)) 研究分担者
・平成17年4月-平成20年3月 (基盤研究(B)(一般))17320138 研究課題:地域資源としての<景観>の保全および活用に関する民俗学的研究(研究代表者:岩本通弥(東京大学)) 研究分担者
科学研究費補助金
・平成28年4月-平成31年3月 (基盤研究(C))16K03225 研究課題:かくれキリシタンの近代における変化と文化遺産化に関する民俗学的研究 研究代表者
・平成26年4月-平成30年3月 (基盤研究(C))26520107 研究課題:高齢化が進む離島集落の再編に資する横断的研究(研究代表者:安武敦子(長崎大学)) 研究分担者
・平成26年10月-平成28年3月(予定) (研究活動スタート支援)26884034 研究課題:生きている信仰・カクレキリシタンの文化遺産化と世界遺産の影響に関する民俗学的研究 研究代表者
・平成25年4月-平成28年3月(予定) (挑戦的萌芽研究)80128181 研究課題:戦争記憶の表象における社会的マイノリティの位置-長崎をフィールドとして(研究代表者:佐久間正(長崎大学)) 研究分担者
・平成24年4月-平成27年3月(予定) (挑戦的萌芽研究)24653120 研究課題:メモリー・スタディーズのモデル構築に向けた領域横断的研究―東アジアを事例として(研究代表者:葉柳和則(長崎大学)) 研究分担者
・平成23年4月-平成26年3月 (基盤研究(B)(一般))23310035 研究課題:世界自然遺産の再資源化に向けたアクションリサーチ(研究代表者:柴崎茂光(国立歴史民俗博物館)) 研究分担者
・平成22年4月-平成25年3月 (基盤研究(C)(一般))22520827 研究課題:茅葺き技術の継承と応用に関する民俗学的研究 研究代表者
・平成20年4月-平成23年3月 (基盤研究(B)(一般))20320133 研究課題:文化財保護制度における世界遺産条約の戦略的受容と運用に関する日韓比較研究(研究代表者:岩本通弥(東京大学)) 研究分担者
・平成19年4月-平成22年3月 (若手研究(B))19720236 研究課題:「合掌造り」を事例とした近代における民家の価値転換に関する民俗学的研究 研究代表者
・平成18年4月-平成20年3月 (基盤研究(B)(一般))18320141 研究課題:家族写真の歴史民俗学的研究(研究代表者:川村邦光(大阪大学)) 研究分担者
・平成17年4月-平成20年3月 (基盤研究(B)(一般))17320138 研究課題:地域資源としての<景観>の保全および活用に関する民俗学的研究(研究代表者:岩本通弥(東京大学)) 研究分担者
研究指導が可能なテーマや領域
日本における文化の表象・継承・活用に関する研究。
【研究指導(ゼミ)の使用言語】
日本語
日本語
過去に指導した修士論文・学部卒業論文等のタイトル
修士論文
「長崎県下におけるカクレキリシタン習俗の比較研究-外海と五島列島を中心として-」
卒業論文
「路面販売の生き残り策-長崎市住吉町の事例を通して-」
「肥前のやきもの・志田焼の歴史的変遷-近代における盛衰を中心に-」
「近代盆踊り考-福岡県京都郡苅田町を事例にして」
「長崎県の綱引きに関する一考察」
「神役の空白による祭祀の衰退と現状-沖縄県宮古島狩俣のウヤーンを事例として-」
「長崎市池島における地域おこしの現状と課題-炭鉱からツーリズムへ-」
「地域ブランドの創出と地域活性化の行方-「ド・ロさまそうめん」を事例として-」
「島原手延素麺の現状と課題」
「長崎華僑における社会組織の歴史と変遷」
「コスプレの地域差に関する研究-長崎の事例を中心として-」
「長崎における鯨歯工芸の現状」
「国営大和干拓と入植農家たちの葛藤」
「歴史文化を活かしたまちづくりと観光-長崎市南山手を事例として-」
「震災前後での町屋及び町並み保全活動の変容-熊本市新町古町地区を事例に-」
「唄オラショの二次的・三次的活用の実態」
「リゾート開発と地域振興-長崎市伊王島を事例として-」
「長崎県下におけるカクレキリシタン習俗の比較研究-外海と五島列島を中心として-」
卒業論文
「路面販売の生き残り策-長崎市住吉町の事例を通して-」
「肥前のやきもの・志田焼の歴史的変遷-近代における盛衰を中心に-」
「近代盆踊り考-福岡県京都郡苅田町を事例にして」
「長崎県の綱引きに関する一考察」
「神役の空白による祭祀の衰退と現状-沖縄県宮古島狩俣のウヤーンを事例として-」
「長崎市池島における地域おこしの現状と課題-炭鉱からツーリズムへ-」
「地域ブランドの創出と地域活性化の行方-「ド・ロさまそうめん」を事例として-」
「島原手延素麺の現状と課題」
「長崎華僑における社会組織の歴史と変遷」
「コスプレの地域差に関する研究-長崎の事例を中心として-」
「長崎における鯨歯工芸の現状」
「国営大和干拓と入植農家たちの葛藤」
「歴史文化を活かしたまちづくりと観光-長崎市南山手を事例として-」
「震災前後での町屋及び町並み保全活動の変容-熊本市新町古町地区を事例に-」
「唄オラショの二次的・三次的活用の実態」
「リゾート開発と地域振興-長崎市伊王島を事例として-」
受験希望者へのメッセージ・リクエスト
自分の関心のあるテーマだけでなく、民俗学・文化人類学の文献を幅広く読み、知識を蓄えてきてください。その上で、自分の研究テーマに関しては、領域横断的に目配りをして、問いを深めてほしいと思っています。