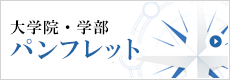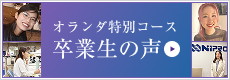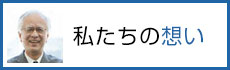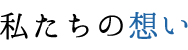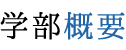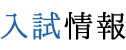大学院の紹介
教員紹介
木村 直樹

長崎で世界と日本の歴史的つながりを探求する
木村 直樹(きむら・なおき)
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程中退、日本近世史、博士(文学)、2000年度より2012年度の間、東京大学史料編纂所附属画像解析史料センターで歴史情報処理を担当した後、同所近世史料部門で『大日本近世史料 細川家史料』という歴史史料集の編纂に従事。
2014年4月より長崎大学多文化社会学部。
⇒研究歴等の詳細へ
| 職位 | 教授 |
|---|---|
| 学位 | 博士(文学) |
| 専攻 | 史学 |
| 研究分野 | 日本近世政治史・対外関係史・日蘭関係史 |
| 担当授業科目 (博士前期課程) |
学問のエレメンツⅠ: 人文科学(歴史)、日本近世史・日蘭交流史特講、日本近世史・日蘭交流史特定演習、多文化社会学セミナー、研究指導 |
| 担当授業科目 (博士後期課程) |
多文化社会学特論Ⅰ、研究演習Ⅰ、研究演習Ⅱ、研究指導 |
|
n-kimura●nagasaki-u.ac.jp ※●を@に置き換えて送信してください。 |
研究テーマ
(1)日蘭関係(特に情報論)からみた日本近世対外関係史
(2)近世都市長崎と対外関係の関係性の研究
(3)島原の乱の国制的研究
(4)寛永飢饉の研究
(2)近世都市長崎と対外関係の関係性の研究
(3)島原の乱の国制的研究
(4)寛永飢饉の研究
研究の内容や方法
オランダや九州を中心とした日本各地に残る近世日本の長崎や対外関係にかかわる史料を調査し、一つの事件や歴史的出来事を、様々な立場から作成された史料に基づいて、多角的に分析する方法で、研究テーマの解明に挑んでいる。
研究成果
【主たる著書】
『長崎奉行の歴史 苦悩する官僚エリート』(単著、角川書店、2016年)『〈通訳〉たちの幕末維新』(単著、吉川弘文館、2012年)『幕藩制国家と東アジア世界』(単著、吉川弘文館、2009年) 歴史学研究会編『世界史史料第12巻 21世紀の世界へー日本と世界16世紀以後』(共著、岩波書店¸2013)横山伊徳編『オランダ商館長の見た日本―ティツィング往復書翰集―』(共著、吉川弘文館、2005年)『大日本近世史料 細川家史料 第20~23巻』(共著、東京大学出版会、2006~2012年)
『長崎奉行の歴史 苦悩する官僚エリート』(単著、角川書店、2016年)『〈通訳〉たちの幕末維新』(単著、吉川弘文館、2012年)『幕藩制国家と東アジア世界』(単著、吉川弘文館、2009年) 歴史学研究会編『世界史史料第12巻 21世紀の世界へー日本と世界16世紀以後』(共著、岩波書店¸2013)横山伊徳編『オランダ商館長の見た日本―ティツィング往復書翰集―』(共著、吉川弘文館、2005年)『大日本近世史料 細川家史料 第20~23巻』(共著、東京大学出版会、2006~2012年)
【主たる論文】
「近世長崎研究の現在」(『歴史評論』799号、2016年) 「近世の対外関係」(『岩波講座日本歴史第11巻近世2』岩波書店、2014年)
「近世長崎研究の現在」(『歴史評論』799号、2016年) 「近世の対外関係」(『岩波講座日本歴史第11巻近世2』岩波書店、2014年)
【外部資金獲得、受賞等】
「戦功書上から由緒へ―兵からみる兵農分離、九州北部分散所在型武家文書を事例に」(研究代表者、2016 – 2018、基盤研究(C) )、「近世国家境界域「四つの口」における物資流通の比較考古学的研究」( 研究代表者渡辺 芳郎、2016 – 2020年度、基盤研究(B) )、「歴史知識情報のオープンデータ化にむけたスキームと情報利活用手法の再構築」(研究代表者久留島 典子
2014 – 2018年度、基盤研究(A))、「 歴史的文字に関する経験知の共有資源化と多元的分析のための人文・情報学融合研究」(研究代表者 馬場 基、2014 – 2017年度、基盤研究(A) )など
「戦功書上から由緒へ―兵からみる兵農分離、九州北部分散所在型武家文書を事例に」(研究代表者、2016 – 2018、基盤研究(C) )、「近世国家境界域「四つの口」における物資流通の比較考古学的研究」( 研究代表者渡辺 芳郎、2016 – 2020年度、基盤研究(B) )、「歴史知識情報のオープンデータ化にむけたスキームと情報利活用手法の再構築」(研究代表者久留島 典子
2014 – 2018年度、基盤研究(A))、「 歴史的文字に関する経験知の共有資源化と多元的分析のための人文・情報学融合研究」(研究代表者 馬場 基、2014 – 2017年度、基盤研究(A) )など
研究指導が可能なテーマや領域
日本近世史、特に日蘭関係史や政治外交史、長崎を中心とした九州の地域史
【研究指導(ゼミ)の使用言語】
日本語
日本語
受験希望者へのメッセージ・リクエスト
歴史学の基本は、史料を読み解き、議論をすることにあります。史料をよむことをいとわない方と、ぜひ一緒に研究をいたしましょう。