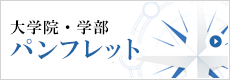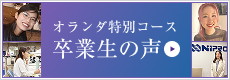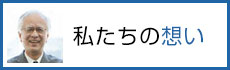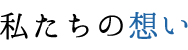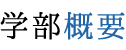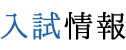学部からのお知らせ
高校生のためのグローバルリーダーゼミ@東京
2013/11/25 トピックス
日経Bizアカデミー×長崎大学Presents「飛び出せ世界へ!高校生のためのグローバルリーダーゼミ」
2013年10月27日開催(ライター:川良真理)
長崎から世界へ
それも選択肢のひとつ
JR市ヶ谷駅のホームに降り立つと、目に飛び込む「TKP」の文字。
このTKP市ヶ谷カンファレンスセンターの最上階大ホールに、首都圏の高校から自由参加で200人が集まった。
なかには親子での参加者もあり、後方の保護者席も賑わっている。
ゼミはまず、片峰茂・長崎大学学長の挨拶から始まった。

▲開会の挨拶をする片峰茂・長崎大学長
「長崎大学の多文化社会学部の設置が文部科学省から正式に承認 されました。キーワードは『グローバル人材の育成』。今や大学は個性の時代。その個性を見極めて、長崎から世界を目指すというチャレンジも選択肢に入れていただきたい」と会場の高校生へ笑顔で語りかける。
基調講演となるキーノート・スピーチは、メディアでもおなじみの東進ハイスクール講師の安河内哲也氏。

▲安河内哲也氏によるキーノート・スピーチ。客席を巻き込んでの、あっという間の50分間
「私のミッションは、この会場にいる人たち全員を外国に送り出すこと」という切り出しに、会場が小さくどよめく。「どうして僕らは外国に行かなければいけないのか?まずそのメリットをシートに書いて発表してみて。発表してくれた人にはオリジナルTシャツをプレゼント、はい!そこのあなた」。スピード感のある語り口とステップワークでステージを所狭しと動き回り、見る間に参加者を自分のペースに引き込んでいくさまは、さすがの一言!
「思考のスコープを拡大していくこと。まずは長崎、それから世界。長崎は江戸時代の国際交流拠点だったよね」「学生時代の外国経験の一つ一つが、自分のキャリア、仕事のヒントになる」といった説得力のある言葉が次々と繰り出され、50分があっという間に過ぎていく。
講師と高校生が丁々発止のやりとり
「このアイデアは使える!」
すっかり会場の雰囲気が盛り上がったところで、4つの講座別に部屋を移動。ここからは各講座に長崎大学の先生方がモデレーターとして参加し、講師とともにそれぞれのテーマに沿った、密度の濃いディスカッションが繰り広げられる。
Aコースは、基調講演を行った安河内哲也氏×葉柳和則教授による「英語が苦手なキミを救うとっておきの勉強法」。自己紹介のコツなども伝授され、これはすぐに応用できそう。
Bコースは、2007年の「ヤング・グローバル・リーダー」150人にも選ばれた高島宏平氏×源島福己教授による「“夢中”を見つけて世界の舞台に立つ」。小グループに分かれ、7年後の東京オリンピックに向けて日本ならではの企画をたてよ、という課題に取り組む。
Cコースは、弁護士であり国際NGOで活躍する土井香苗氏×広瀬訓教授による「世界のためにわたしたちができること」。世界の紛争地域の現状とNGOの活動を学んだうえで、軍事利用されている学校を子どもたちの手に取り戻すための方法についてアイデアを出し合う。
Dコースは、バングラデシュのグラミン銀行初の日本人コーディネーターとなった税所篤快氏×増田研准教授による「最高の授業を世界の果てまで届ける仕事」。まだ20代という税所氏の行動力にインスパイアされながら、駆けつけてくれた実際のグラミン銀行の担当者に対して班別に英語でプレゼンテーションを行う。
どの会場でも、講師のみなさんは高校生たちに自身の仕事についてとても熱心に語っている。いずれも各界の第一線で、世界を舞台に活躍するフロントランナー。こんな至近距離で、しかも直接言葉を交わしながら話が聞ける機会は、そうあることではない。それを聞く高校生の参加者たちもメッセージをしっかり受け止め、ときに自分の思いをぶつける。その丁々発止のやりとりが熱くて面白い! 「思った以上にみんなのアイデアは素晴らしいよ! みんながやらないなら僕が実現しちゃおうかな」と講師がつぶやく一幕も。モデレーターの長崎大学の先生方も高校生たちに気軽に声をかけて回り、また長大生のサポーターも輪のなかに入り、共にプレゼンをするなど、会場を盛り上げる。


▲
(写真左)安河内哲也氏×葉柳和則教授によるゼミ「英語が苦手なキミを救うとっておきの勉強法」
(写真右)高島宏平氏×源島福己教授によるゼミ「“夢中”を見つけて世界の舞台に立つ」


▲
(写真左)土井香苗氏×広瀬訓教授によるゼミ「世界のためにわたしたちができること」
(写真右)税所篤快氏×増田研准教授によるゼミ「最高の授業を世界の果てまで届ける仕事」
最後は交流会。今回はそれぞれが高校からの自由参加だっただけに、最初はおとなしかった参加者同士。しかし、ゼミでは同じ班でプレゼンをし、会話練習をしたこともあり、この頃にはすっかり打ち解けた様子。多文化社会学部について教員に詳しく尋ねる高校生、パネルを見入って話し込む参加者や保護者もちらほら。
学長が冒頭に語った「長崎大学の個性」についても、メディアやネット、紙の資料などでは得られない、生の姿が伝わったのではないだろうか。

▲交流会で高校生と言葉を交わす片峰学長、安河内氏
⇒一覧に戻る